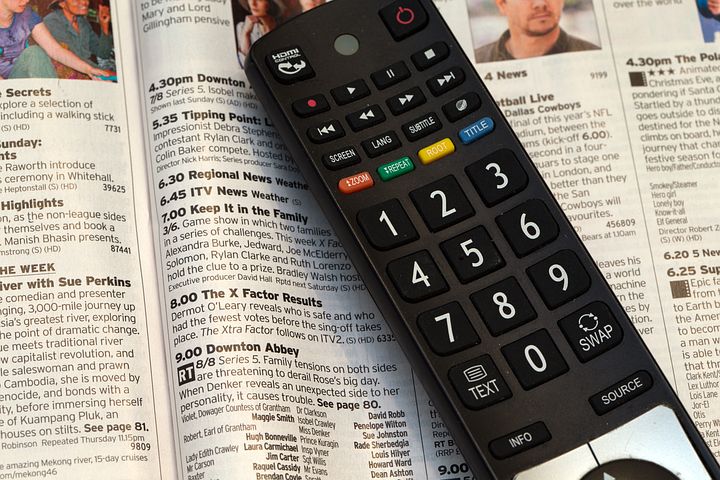先日関西系列の地上波番組が、「脱毛エステでトラブル急増」というテーマで放送をされていました。概要だけお伝えすると、とある脱毛エステサロンを利用していた消費者の女性が被害を訴えており、内容は以下のようなものになります。Aさんは従業員から勧められ30年間の脱毛通いたい放題の契約をされました。従業員から推奨されていた来店頻度は3ヶ月に1回でしたが、「サロンが人気で予約が取れない」ということを理由に早期のタイミングで半年に1回しか予約がとれない状況になってしまいました。不満ながらもAさんは脱毛サロンに半年に1回通い続けましたが、9回目の来店にして「次回からの脱毛は、セルフで行ってください」とお店から通達され、挙げ句にはこの脱毛サロンは閉店し、連絡も以後Aさんと取れなくなってしまいました。
これは2017年に劣悪な業者が引き起こした一例なのですが、こういった事例の報告が積み重なり、令和5年には消費者法が改正されました。弊社のサポートするどのエステサロンでも、健全経営を念頭に実務に日々励んでおられますが、法改正の概要を適切に理解し営業・接客スキームを見直すことは重要事項となるでしょう。
【目次】
1.エステサロン事業者が注視すべき、「消費者契約法の改正」について
2.エステサロンで使用する同意書の内容を、もう一度見直しましょう
3.今回のまとめ
エステサロン事業者が注視すべき、「消費者契約法の改正」について
私たちエステサロン事業者にとって注視すべきは消費者契約法の改正であるといえます。消費者契約法の概要とは、一般消費者と(ここでいうエステサロン)事業者が交わす取引について、民法によるルールにおいて消費者を保護できる方向で修正できる法律です。例えばエステ化粧品メーカーがエステサロン事業者と交わす取引においては、当事者同士が公平な形式で民事のルールは左右をするといいます。しかしながらエステサロンに通う一般消費者は、ビジネスに関する知識や経験が当然不足しているわけですから、そういう不利である立場の人たちを補うために法律が定められており、これが消費者契約法であります。
冒頭の事例に関しては、エステサロンに通うAさん・エステサロン事業者という当事者相関図でありますから、消費者契約法はAさんにとって、一方的に不利益な契約内容があればそれは無効になったり、契約そのもの取り消しを認めることができるルールにもなります。この時のAさんはサロン側から「無制限コースの場合、8回目まで有償、9回目以降は無償サービス提供とさせて頂きます」といった同意書に押印し、60万円以上のコースを「いま契約すれば30万円」という営業を受け契約をしました。消費者契約法の改正とAさんに起きた事象は、大きな関連性があるといえます。
エステサロンで使用する同意書の内容を、もう一度見直しましょう
消費者契約法の改正は具体的に、「契約の取り消しの追加」です。本来民法では消費者がエステサロンと交わした契約を打ち消すことができる場合は「騙されて契約した(つまり詐欺)」に限定されていましたが、消費者契約法の改正はこの範疇を拡大したことを意味します。今回の法改正では「勧誘することを告げずに消費者を退去困難な場所へ同行して勧誘した場合」・「消費者を威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害した場合」・「契約前に契約の目的となる物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にした場合」といった三点が、要件に含まれました。そして事業者の努力義務の拡充という要件も法改正によって加えられました。例えばそれは、契約を解除する場合について、解除するケースで必要な内容の情報提供を事業者はしっかり行ったり、解約料の算定根拠の概要を説明するように努力をすることが求められるということが挙げられます。
Aさんの事案は、法改正以前だったとしても取り締まられるような詐欺に近いようなものですが、同意書の内容が不透明且つ説明責任を果たしていませんし、契約のサービス内容は著しく変更しているとしかいいようがありませんから、違法性を更に問えるべき案件だとメディアや専門家たちは発信しています。
今回のまとめ
エステサロンだけではありませんが、同業他社がこのような劣悪なサービスをメディアから告発されたとき「自社のエステサロンも印象が悪くなる。いい迷惑だ」と思うことは仕方ないことだと思います。しかしながらこういった業者に被害に遭った消費者の方々が誠実なエステサロンと巡り合うことができたとき、店舗の価値はより眩しく映りますから、努力を怠らず誠実に事業に取り組むことこそがエステサロン経営にとってもっとも大切なことだと私たちは考えます。